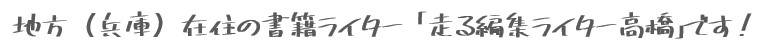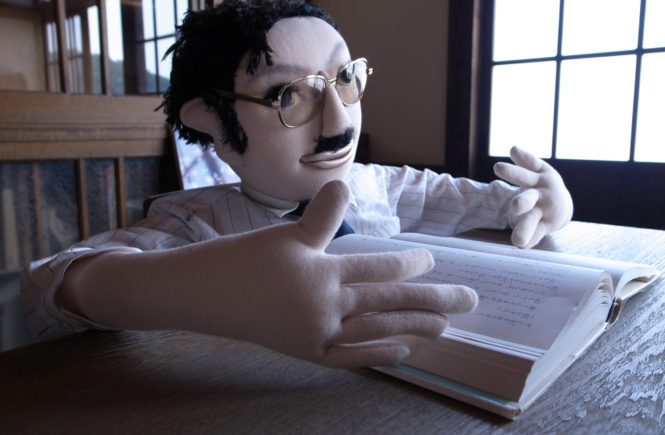故・桂米朝師匠の落語が好きで車でたまに聴いています。
なかでもお気に入りは「天狗裁き」。
妻が旦那の(見てもしない)夢を聞き出そうとして夫婦喧嘩に発展し、その喧嘩の仲裁に入ったひとも次々その旦那に夢を聞かせろと脅かし、最終的に天狗が旦那を裁こうとしてしまうまでの顛末をそれはそれは面白おかしく語り上げます。車なので音声のみで聴いていますが、登場人物の表情までもが浮かんできそうなほどの迫真の語りです。
その米朝師匠の天狗裁き。本題に入る前の枕で、江戸時代の小噺が紹介されています。要約すると次のとおり。
夢を見た。どんな夢? なすびの夢を見た。それは大きななすびやった。どれくらいの大きさや? この家ぐらいあったんか? そんなもんやない。そやなあ、ものにたとえたら「暗闇にへた付けたような……」
暗闇という無限のサイズ感を利用したたとえ噺で、聞いた瞬間に錯覚を覚えるような独特の広がりがなんか斬新です。本題とはちがいますが、毎回聴き入ってしまう好きな箇所です。
***
きょうも仕事終わりに車で帰宅中、天狗裁きのなすびの噺の箇所を聴いていたとき、糸井重里さんの次のコピーをふと連想しました。
夢に手足を。
夢が自分で勝手に歩いていくイメージが浮かんできて面白いです。夢となすび、無限のサイズ感という点でなんとなく共通点があるといえなくもない(?)と思ったり。広告のキャッチコピーは好きじゃないけど、やっぱり超一流のひとが考えることばは違います。
***
きょうはエイプリルフール。
各社ホームページで趣向を凝らした〝嘘〟をついていて、何社かの遊び心を楽しみました(たとえばタカラトミーとか)。嘘も方便というように、場合によってはその嘘が人の気持ちを和ませたりすることもあるんですね。
嘘まではいかなくとも、ときに法螺は必要といわれます。
ぼくもそうですが、日本人は法螺を吹くのが苦手みたいです。日本人は10できることでも7しかできないと謙遜する一方、外国人は7しかできなくても12できると大風呂敷を広げる、みたいな。
ぼくも含めた日本人、法螺に手足をくっつけるくらいがちょうどいいかもしれません。自分の法螺が勝手に歩いていって収拾がつかなくなり、それをやらざるを得ない状況になって努力し、振り返ってみるとそれがきっかけで成長していました、みたいな。
……というようなことを、天狗裁きから連想した4月1日でした。