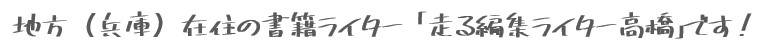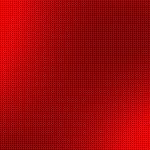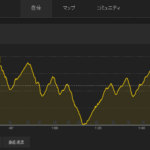司馬遼太郎の『国盗り物語〈1〉斎藤道三〈前編〉 (新潮文庫)』を読んでいてこんな場面に遭遇しました。
美濃へ来て、七か月たつ。
大永二年の春、西村勘九郎こと庄九郎は、鷺山殿へ伺候(しこう)し、頼芸に、懇願した。
「財産などの整理もあり、いちど京に帰りたいと存じまする」
「帰りたい?」
頼芸は、いい顔をしない。
「勘九郎。帰る、という言葉がおだやかではない。そのほうの本貫は美濃ではないか。まだ、美濃に腰をおろすつもりにはなってくれぬのか」
「いや、これは不覚でござりました。京へのぼる、と申さねばなりませぬ」 P275
西村勘九郎こと庄九郎、ことのちの斎藤道三は京都の油屋を継いだのち、国盗りの意を秘めて美濃(岐阜)に単身入り、守護職の弟・頼芸(鷺山殿)に認められて美濃の名族・西村屋を継承することになります。
西村屋を継いだことで庄九郎(道三)は美濃の人間になったのだから、「京へ帰る」ではなく、「京へのぼる」と口のするのが正道だろう、これが庄九郎に期待を寄せる頼芸の言い分。
***
この場面を読んでいてふと思い出しました。
ぼくは高校を卒業する18歳まで実家の兵庫県加東市で暮らし、高校卒業後は大阪府枚方市で10年、兵庫県尼崎市で8年過ごしたのち、36歳のときに実家にUターンしました。
実家を離れていたあるとき、子どもの頃からお世話になっている叔母さんから言われて強く印象に残ったことばがあります。
「大阪に〝帰る〟んとちがうで、〝行く〟んやで。帰るというのは、ここ(実家)に帰ってくるときに使うことばやから」
実家を出て月日が経つほどに、叔母さんから言われたこのひと言が心にしみ、「帰る」と「行く」を意識的に使い分けていたのを思い出します。その感慨が、国盗り物語の一節でよみがえったのでした。
***
「帰る」と「行く」は、自分の所在を決定づける、とてもとても大切な使い分けなのに、叔母さんに言われるまで気づきませんでした。使い方を間違えば、相手に寂しい思いをさせてしまう可能性すらある、と学びました。
これは一例ですが、自分の立場や立ち位置によって求められることばが違ってくるケースはたくさんあります。敬語はその最たる例ですね。司馬遼太郎の世界にひたりながら、相手を慮ったことばの使い方、たいせつにしたいなあとあらためて思ったのでした。